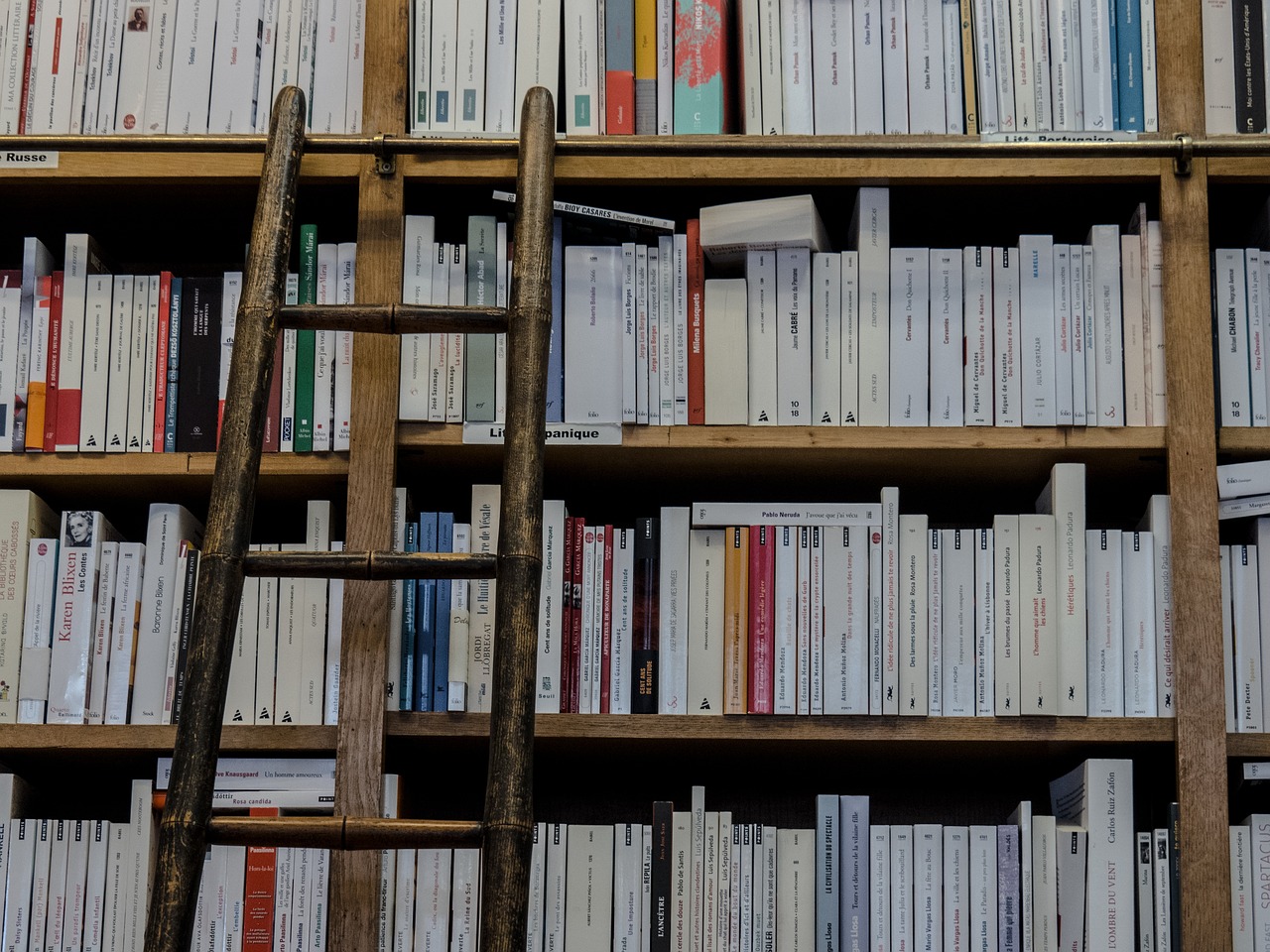「IT業界では、日々勉強し続けないといけない」そんな言葉を、ITエンジニアを目指す人や、就職・転職活動中の方はよく耳にすると思います。たしかに、それは事実です。
でも、その言葉だけを聞くと、なんとなく大変そうだし、ずっと勉強しなきゃいけないのか……と、少し尻込みしてしまうかもしれません。
しかし視点を変えれば、IT業界は「学び続けることが当たり前として受け入れられる数少ない業界」であり、学習したことがそのままキャリアや収入に直結する“自己投資効果の高い世界”でもあるのです。
今回は、「なぜIT業界では学習が避けて通れないのか」、「それがなぜ自己投資なのか」、そして「どう学んでいくと良いか」という点について、順を追って説明します。
なぜIT業界では学び続けることが前提なのか
技術の変化が早すぎる
まず学習することが避けられない一番大きな理由は、技術の変化スピードが圧倒的に早いことです。
たとえば、今主流だったフレームワークや開発言語、クラウドのベストプラクティスは、5年後には“古い技術”とされている可能性は大いにあります。
スマートフォンアプリ、AI、クラウド、ブロックチェーン、IoTなど、新しい技術が次々に登場し、そして実際の現場で使われ始めます。
登場する技術を学び続けなければ「すぐに使えない人」になってしまうのがこの業界の特徴です。
新しい分野ほど市場価値が高い
逆に言えば、新しいことをキャッチアップできる人材は、市場価値が高くなります。
流行の技術、あるいは難しい分野を「今学んでいる」というだけで、転職市場での評価が変わることもあるほどです。
学び=自己投資になる理由
スキルが直接収入や評価につながる
多くの職業では、「学んでも給料が上がるとは限らない」、「何年勤めても評価されない」といった声をよく聞きますが、IT業界はそこまで悲観的ではありません。
特定の資格を取った、スキルセットを広げた、得意分野のポートフォリオを作った、など“見える努力”は比較的評価されやすいといえると思います。
特にフリーランスエンジニアや副業をしている人にとっては、学んだ技術を即座にサービスやプロジェクトに反映できるので、「学んだ分だけお金になる」ことを実感しやすいでしょう。
キャリアの選択肢が広がる
ある分野に特化して深く掘ることで「スペシャリスト」になれる一方で、複数の分野を浅く横断的に理解して「ジェネラリスト」として活躍する道もあります。
学び方次第でキャリアの幅を自在に広げられるのも、IT業界ならではの魅力です。
たとえば、Webエンジニアがセキュリティ分野の知識を身につければ、セキュリティエンジニアへのキャリアチェンジも現実的です。
逆にインフラエンジニアがPythonを学び、AI開発に関わる道を拓くことも可能です。
https://ict-garage-jp.com/introduction-to-senavi/
学びを継続するためのコツ
完璧を目指さず、小さく始める
「全部理解してからじゃないと次に進めない」
「技術書を最初から最後まで読まないと気がすまない」
こうした完璧主義は、学習を継続するうえで足かせになることがあります。
最初は理解できなくても、手を動かしながら少しずつ学ぶ姿勢が大切です。プロジェクトを作る過程で、自然と深く理解できることも多いです。
少しづつでも学習を進めることで、そのうちに点と点が繋がって線になる。そういった実感を得ることができると思います。
仲間と学ぶ・発信する
一人で黙々と勉強していると、モチベーションが下がってしまうこともあります。そんなときは、コミュニティや勉強会に参加する、SNSで学びを発信するといった方法が効果的です。
仲間がいると、自然と刺激になり、継続しやすくなります。
学んだことはアウトプットする
学習効果を高めるには、「学んだら使う」、「誰かに説明してみる」というアウトプットがとても重要です。
業務で使うだけでなく、QiitaやZenn、技術ブログに書くことも良い方法ですし、社内でのLT(ライトニングトーク)やチーム内でのシェアも、学びを定着させるうえで役立ちます。
最後に:未来の自分のために、今学ぼう
IT業界は、一度身につけた技術が10年後にも通用するとは限らない、変化の激しい世界です。しかし同時に、「今日の学びが、来月の仕事を変える」ことも起こり得ます。
極めて、学びがリターンにつながりやすい世界でもあるのです。
時間がない、モチベーションが湧かない、そう感じることもあるかもしれません。
それでも、少しでも早く、少しずつでも学びを始めることで、未来の自分が大きな恩恵を受けることになります。
“学び続ける姿勢”こそが、IT業界で長く活躍するための最大の武器です。
https://ict-garage-jp.com/introduction-to-dmmwebcamp/
最後までお読みいただきありがとうございました。当ブログは日常のICTの困りごとを解決するためのノウハウを発信しているサイトです。トップページもご覧ください。